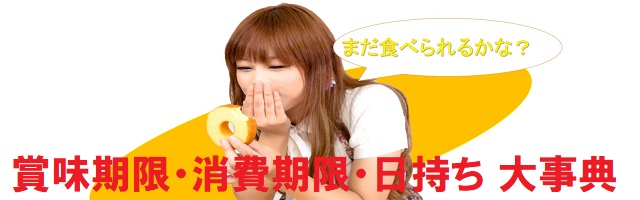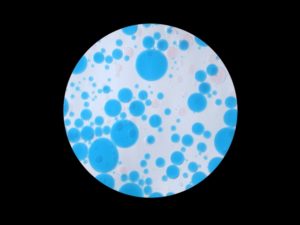串カツの賞味期限とソース二度付け禁止の秘密とは
大阪の食い倒れグルメの一つ「串カツ」。
どのくらいの期間食べられるのでしょうか。
揚げる前、揚げた後、それぞれの賞味期限・消費期限など日持ちをお知らせします。
ソース二度付け禁止の秘密もお知らせしま ...
横浜名物 崎陽軒のシウマイ弁当の賞味期限と秘密|5つ目が斜めに並んでいる理由とは
横浜の崎陽軒と言えばシウマイです。
お土産としても人気で、東京駅や羽田空港でも売られているほどです。
そのシウマイが食べられるシウマイ弁当の賞味期限と秘密についてお知らせします。
地鶏は普通の鶏とは違う|おいしくなるための3つの要素とは
一般的に「地鶏」と言うと、炭火で焼かれたものがメジャーです。
印象としては「硬い」ではないでしょうか。
これは、調理方法を間違えているのと、肉自体がそれほど良くない地鶏なのかもしれません。
本当に良 ...
手作りアップルパイの賞味期限・消費期限・日持ち・保存方法とは
記念日や誕生日に作られるアップルパイ。
手作りスイーツの中でも人気が高いです。
余ってしまったアップルパイはどのぐらい持つのでしょうか?
また、保存方法はどのようにしたらいいのでしょうか
【驚愕の事実】ヨーグルトの「乳酸菌」と「ビフィズス菌」は別のものだった
「ヨーグルトは体にいいですか?」と聞いたら10人中10人が「体にいい」と答えるでしょう。
では、「乳酸菌」と「ビフィズス菌」はどちらが体にいいでしょう?」と聞いたら、多くの方が「え!?同じものじゃないの!?」と答えます。